私が2025年1月に読んだ9冊の本をオススメ順に紹介します。
小説、ビジネス書などジャンルを問わず、気になった本はどんどん読むことにしています。
今月は、意識せずとも「考える」ということ、さらには「自分自身を知る」ということの大切さを突き付けられる1ヶ月となりました。
【1】いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才 / 今井 孝
日々の実践に生かしやすいこちらの書籍をまず紹介させてください。
内容が明確なので分かりやすく、この方法なら自分でもできるかも!とワクワクしました。
充実した1日は、自分を幸せにしてくれる2時間からつくられる
タイトルで大変魅力的なワード『2時間』。
必要なことは、本当に自分を幸せにしてくれるたった2時間をつくること
24時間365日頑張り続ける必要はなく、
1日のうちの2時間が幸せな時間であれば毎日が充実するとのこと。
ではその『幸せな2時間』を過ごすにはどうすればよいのかについて解説されているのが本書です。
幸せな2時間の生み出し方
本書では具体的に、
- 無駄な時間の減らし方
- 何が自分を幸せにしてくれるのかを知る
- スケジュールに落とし込む
といった形で幸せな2時間の生み出し方を教えてくれています。

私にとって無駄な時間ってなんだろう…?
考えてみたところ色々でてきました。
- SNSをダラダラ見ている時間
- 実家、義実家、家族に対してモヤモヤする時間
- 夕飯の副菜を悩む時間
- 旅先の天気に一喜一憂する時間
などなどなど・・・
解決策も考えてみました。
- SNSをダラダラ見ている時間⇒アプリ使用時間制限を1日10分に設定(設定済み!)
- 実家、義実家、家族に対してモヤモヤする時間⇒期待しない、考えない・・・
- 夕飯の副菜を悩む時間⇒レパートリーを5つ用意
- 旅先の天気に一喜一憂する時間⇒気にしない
ちなみに、
天気など自分でコントロールできないことに一喜一憂する時間は
『いますぐやめるべき5つのムダ』の1つとして紹介されていました。
継続することの大切さ
最近読んだ別の本にも記載されていましたが、
小さなことを積み重ねることの重要性にも言及されています。
あなたがこの10年で成し遂げたいことは何ですか?
この問いに対する答えが1つに定まらないのが現状ではありますが
今1つに決めて他を捨てるのではなく、
自分が好きなことはちょっとずつ進めてみて
定期的に同じ問いかけをしてみたいと思っています。
【2】さみしい夜にはペンを持て / 古賀 史健
こちらは日記に関する本です。
私もスマホの日記アプリに日記をつけているので、
自分のやっていることを肯定してもらうようなつもりで手に取った一冊ですが
『その日になにがあったのか』を書いていくんじゃなくて、『その日になにを思ったのか』や『その日になにを考えたのか』を書いていくものなんだ。
ということでさっそくノックアウトされました。

私の日記には『その日にあったこと』しか書いていませんでした。
『考えたこと』を書き続けた先には『自分自身』を理解する日がくるのだとか…
日記って難しい
ということで読了後、『なにを考えたか』について日記に残そうと奮闘していますが
これが思いのほか難しいのです。
慌ただしく生活していると、なにを考えたかについて記憶に残っていなかったり、
またはだれかにイライラ・モヤモヤした気持ちだけが残っていて
それを丁寧に言語化するのが難しかったり…
そして時間がかかります。
なんとか『ひとりの時間』を確保して続けていきたいです。
そして自分自身のことを知っていきたいです。
ことばの暴力が生まれる理由
日記以外に心に残ったのが、ことばの暴力が生まれる理由について解説されている部分です。
話し合いであれば、ほんとうは自分の思いをていねいに説明して、相手に納得してもらわないといけない。
(中略)
ところが、ていねいに説明するのが面倒くさい。論理的に説明するのも面倒くさい。反論されたら面倒くさい。自分の気持ちをことばにすること自体、面倒くさい。そこに時間や手間をかけることも面倒くさい。そういうさまざまな面倒くささにぶつかったとき、『暴力』という一発逆転の手段が浮かんでくる。暴力に訴えてしまえば、それだけで相手を屈服させることができるからね。
SNS上にはナイフのような言葉があふれています。
私の年齢になれば、そういったものから距離を置いて自由に暮らすことができますが
子どもたちはこれからそれらに直面して生きていかなければなりません。
心苦しいことですが、
だからこそ、ていねいに言葉を紡ぐ練習を私も子どももしていきたいと思えた一冊です。
【3】自分の意見で生きていこう / ちきりん
個人的には『さみしい夜にはペンを持て』の内容と重複する部分が多かったなあと思うのが
こちらの書籍です。
著者である社会派ブロガーのちきりんさんも
若いころから自分が考えたことについて日記に残されていたそうで、
それにより『考える』習慣が身についたとのことです。
『考える』とは?
自分の中でわかってるようで理解できていなかったのが、
- 正解のある問題を解くには『調べる』ことが必要
- 正解のない問題を解くには『考える』ことが必要
という点です。
私たちは学校教育の結果、『調べる(正解にたどり着く)』ことは得意でも
『考える』ことは習慣づけされていません。
『意見』or『反応』
ポジション(自分の立ち位置)が明確なら『意見』
『賛成』『反対』が明確であれば『意見』ということですが、
世の中にはポジションが明確でない『反応』(質問・他者の意見の否定)が多いとのこと。

耳が痛いです。
私自身、賛成・反対のポジションを明確にせず『あーでもない』『こーでもない』と発言をした経験があります。
著者いわく、外資系企業では自分のポジションを明確にしない場合、
議論において同じ土俵にあがらせてもらえないとのこと。
意見と反応を意識的に区別できている人は多くないけれど、市場全体としては
「意見を言っている人=自分のアタマで考えることにより”ゼロからイチ”をクリエイトしている人」と「他者が創り出したコンテンツや意見に反応だけしている人」では明確に区別され、
前者は市場から高く評価される
自分の意見を押し出し続けることで、
『自分』というブランドができあがるイメージでしょうか。
本書では自分の意見を持てるようになる4つのステップも紹介されています。
毎日のニュース・今後起こりうる家族の問題(子どもの教育方針、親の介護など)について
自分の意見をもつように日々意識しようと思えた一冊でした。
【4】十歳のきみへ / 日野原 重明
書籍が発行された2006年時点で95歳の著者が子どもたちへのメッセージを詰め込んだ一冊です。
生きるとは…、人間とは…、平和とは…といった5つのテーマに沿って
著者の思いが子どもにも分かりやすい言葉で綴られています。
生きるとは・・・
からっぽのうつわのなかに、のちを注ぐこと。それが生きるということです。
寿命とは、寿命という大きなからっぽのうつわのなかに、せいいっぱい生きた一瞬一瞬をつめこんでいくイメージです。
あまり変化のない日々を過ごしていると一瞬で過ぎていく時間。
発見や感動がつまった一日一日を過ごせば充実した重みを実感できますよ、というメッセージを読んで
思い当たる節がありすぎました。(笑)
私が10歳のときにこの本に出合えたら違う人生があったのかなあなんて妄想をしたり・・・。
ほかの人のために時間をつかえたとき、時間はいちばん生きてくる
改めて仕事をする理由ってこれだなと気づかせてもらいました。
忙しく仕事をしていると忘れてしまうことですが、
定期的にこの本を手に取って思い出したいです。
想像する力
想像する力が弱くなることが、いちばんこわいことです。
知る力がおそまつになったとき、他人はどこまでも自分とは関係のない存在にしか見えなくなってしまいます。戦争を遠く離れたところから見ているときも、戦争の当事者になってしまったときも、自分のこと以外は理解しようとも知りたいとも思えなくなってしまいます。
これも耳が痛いです。
戦争という大きなテーマで語られていますが、
シンプルに自分の近くにいる人にもっと関心を持とう、
言動の背景を想像するようにしようと思いました。
きみが生まれたとき・・・
きみが生まれたときに、きみのまわりにいた人たちがどんなにしあわせにつつまれたかを、きみは想像したことがありますか。
小さなきみが笑うたびに、きっときみのそばにいただれもが思わずにっこりとほほえみを返したことでしょう。きみがからだいっぱいで泣いていれば、そばにいた、たぶんお母さんは、どんなに用事でいそがしくとも、その手をとめて、きみのもとにかけより、きみをあやしたり、きみがどうしてほしいのかをなんとかわかってあげたいと、いっしょうけんめいになったことでしょう。
この文章だけでも子どもに伝えたい。
我が子が10歳になった日にはこの本を贈ります。
【5】会社のためではなく、自分のために働く、ということ / チェ・イナ
会社員をされている方、転職・独立等を考えられている方におすすめの一冊です。
いまがどんな時期であろうと、重要なのは働いている場所で日々を充実させることだ。最終的には、ぞれらの時間が積み重なって人生ができあがるのだから。
『置かれた場所で咲きなさい』という色が強いです。
ただし、あくまで主役は『自分』です。
自分自身がブランド
「上司や同僚、先輩、後輩、そして顧客は、大事な仕事を私に任せてくれるだろうか?」
「私が一緒にいれば、いい結果が出るはずだと期待してくれるだろうか?」
それから、自分を選ぶべきだと思う理由を書き出してみよう。
その理由こそ、あなたが一つのブランドとして顧客に提供する価値になるだろう。
AIが仕事を処理する世の中になったときでも、
自分にしかできない何かがあれば生き残っていけるということ。
「自分の意見を言う人が市場から評価されるようになっていく」という『自分の意見で生きていこう』と通じるものがありました。
【6】ポンコツなわたしで、生きていく。 / いしかわ ゆき
こちらは逆に『置かれた場所で咲かなくていい』という内容です。
自分が求められる場所のほうが きっとのびのびとラクに根を張れる
知識(本を読むこと)は、生きるのをラクにしてくれる
著者は「どうしても朝起きられず、仕事や約束に遅刻してしまう」ということが悩みで、
それゆえに会社員からフリーランスに転身されたとのこと。
本の内容に100%同意!というところまではいきませんでしたが
『こういう考え方もあるな』というのを知ることができました。

そんなことを考えながら読んでいたところ、まさに同じ内容が。
- 知識(本を読むこと)は、生きるのをラクにしてくれる
- 本を読まないと「考え方」を知らないから、自分に合った考え方を選ぶことすらできない
読書が楽しい理由はここですよね。
私も本を読んで頭の中をアップデートしていこうと改めて思いました。
【7】移動する人はうまくいく / 長倉 顕太
予測不可能な現代
現代は予測不可能な時代だ。ところが、私たち日本人は「答えありきの教育」しか受けてきていないから、予想外の出来事に弱い。当たり前だが、海外では日本のルールは通用しない。そのため、全神経を集中させてサバイバル能力を蘇らせるしかない。
また学校教育の弊害に関する話がでてきました。
著者は、移動すること・定住しないことを推奨しています。
移動すること、新しい場所で暮らすことによってサバイバル能力が目覚めるということで
私もその点は同意です。
また、地方公務員や医療関係者になりたいという若者が多いことについても
以下のように記載されています。
これは国の未来にとても良くない。なぜなら、医療関係の大半は老人に対するものだし、地方なんて老人ばかりだからだ。つまり、若い労働力が老人のために使われているということ。未来ある者の能力や時間を未来の老人に投資されてしまっている。日本が没落している原因の一つがここにある。
一番知りたいのは仕事のこと
では定住せずに暮らす場合、収入はどうすればよいのか。
読者の大半はそこが気になるかと思いますが、おすすめされているのがコンテンツビジネス(YouTuberやブロガーになること)です。
拡大中の市場であり、一般人でも芸能人並みに稼げるということですが
別の章では「子どもにYouTubeは見せるな」という記載も。
お年寄りのための職業に就くことを否定している著者ですが、
コンテンツビジネスを行うことは若者のためになるのか?という疑問がのこりました。
【8】生きるために、捨ててみた。 / だいた ひかる
芸人のだいたひかるさんによる書籍です。
2016年に乳がんが発覚してからのことについて記載されています。
考え方の変化に注目したい
本書では主に断捨離と、考え方の変化について描かれていますが、
「断捨離術」として読もうとすると多少物足りなさを感じます。
ただ、病気が発覚してからの考え方の変化については興味深く、
私も明日何が起こるかわからないということを意識するきっかけになりました。
【9】女はいつも、どっかが痛い / やまざき あつこ
いわゆる更年期障害に関する書籍です。
来るべき日のために手に取りました。
おすすめ順が低いのは、まだ実感がわかないからかと思います。
体のつらさを感じるようになったら再度手に取りたいです。
私たちの生きざまを肯定してくれる
『ああしなさい』『こうしなさい』と決めつけるのではなく、
『どうしても人と比べてしまう』『どうしても我慢してしまう』といった
私たちの生態を『そういう生き物だから!』と肯定してくれるのが
本書の優しいところです。
ただし『寝ながらスマホは百害あって一利なし』ということでしたので、
それだけは守っていこうと思います。
まとめ
2025年1月に読んだ9冊について紹介しました。
特にこだわりなく手に取ったつもりが、内容が重複するものもチラホラ・・・
自分へのメッセージと思って実践していきます。
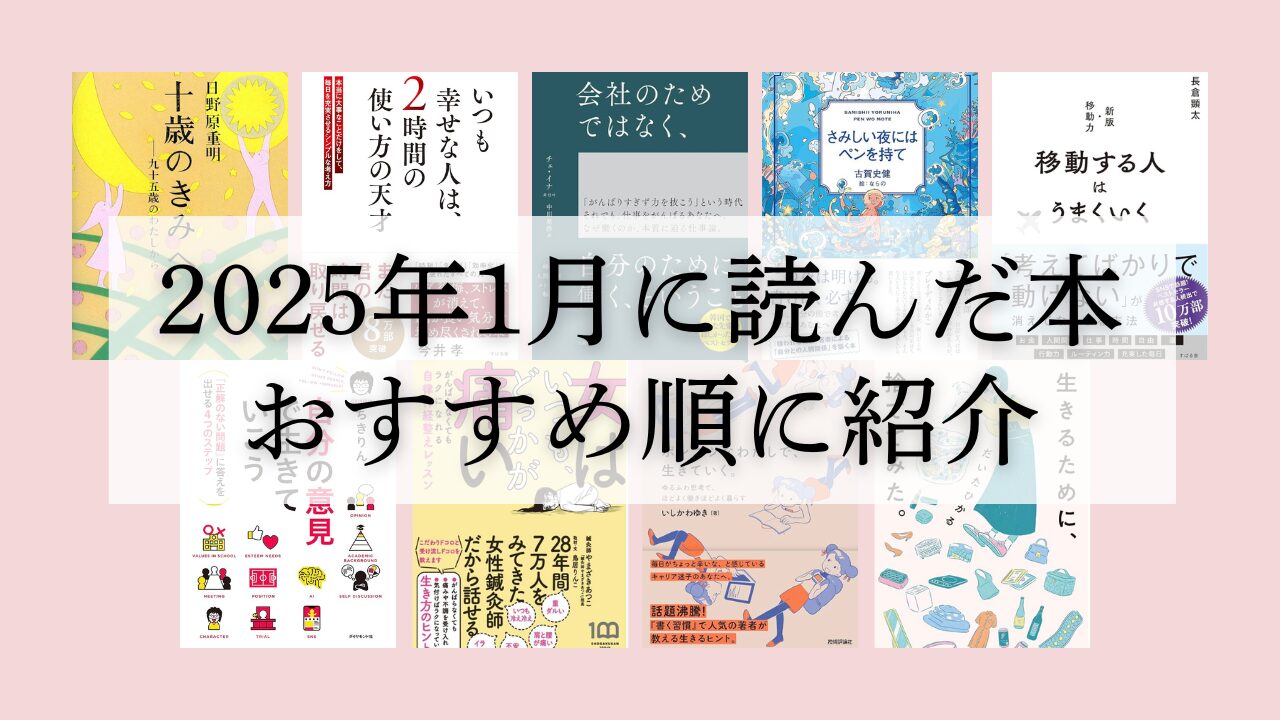

コメント